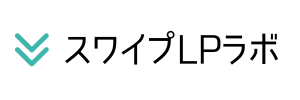「LPの成果がなかなか上がらない」
「どこを改善すればコンバージョン率(CVR)が上がるのか、確信が持てない」
「感覚的な修正ではなく、データに基づいた改善策を実行したい」
Webサイトの成果に責任を持つ担当者の方なら、一度はこのような悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。LPの改善は、まさに事業の成長に直結する重要なテーマです。
そこで有効なのが、データに基づいた客観的な改善手法である「A/Bテスト」です。
A/Bテストを正しく実践することで、LPの課題を特定し、着実にCVRを向上させることができます。
この記事では、LPのA/Bテストについて、初心者の方でも安心して取り組めるように、以下の内容を網羅的に解説します。
- そもそもA/Bテストとは何か、その基本とメリット
- A/Bテストを成功に導く具体的な8つのステップ
- CVR改善に効果的なテスト箇所と仮説の立て方
- 失敗を避けるための注意点
- Googleオプティマイズ終了後の代替ツール
この記事を最後まで読めば、A/Bテストの全体像を理解し、自信を持ってLP改善の第一歩を踏み出せるようになります。
そもそもLPのA/Bテストとは?データで成果を出すための基本

LPの改善において「A/Bテスト」という言葉を耳にする機会は多いでしょう。
しかし、その本質的な目的やメリットを正しく理解することが、成果を出すための第一歩です。
この章では、A/Bテストの基本的な考え方と、なぜそれがLP改善に不可欠なのかを解説します。
感覚的な判断から脱却し、データに基づいた意思決定を行うことの重要性を理解しましょう。
A/Bテストの定義と目的を再確認
A/Bテストとは、特定の要素が異なる2つ(またはそれ以上)のWebページ(Aパターン、Bパターン)を用意し、どちらがより高い成果を出すかを比較検証するマーケティング手法です。
スプリットテストとも呼ばれます。
LPにおけるA/Bテストの最終的な目的は、単にどちらのデザインが良いかを決めることではありません。
コンバージョン率(CVR)を科学的に向上させ、問い合わせや購入といったビジネス上の目標達成に貢献することです。
| テスト手法 | 概要 | 適したケース |
|---|---|---|
| A/Bテスト | 1つの要素だけを変更した2パターンを比較する | 特定の要素(ボタンの色、文言など)の効果を明確に測定したい場合。初心者におすすめ。 |
| 多変量テスト | 複数の要素の組み合わせを同時にテストする | 複数の要素が互いにどう影響するかを分析したい場合。十分なアクセス数が必要。 |
まずは基本的なA/Bテストから始め、どの要素がCVRに影響を与えるのかを一つひとつ特定していくのが成功への近道です。
なぜLP改善にA/Bテストが有効なのか?3つのメリット
A/Bテストを導入することで、LP改善において多くのメリットが得られます。
ここでは、特に重要な3つのメリットをご紹介します。
- データに基づいた客観的な意思決定ができる
社内の意見対立や「担当者の好み」といった主観的な判断を避けられます。
実際のユーザーの行動データが、どちらのパターンが優れているかを客観的に示してくれます。
これにより、上司やクライアントに対しても、改善施策の根拠を論理的に説明することが可能です。 - リスクを抑えながら改善効果を検証できる
LP全体をいきなりリニューアルするのは、成果が悪化するリスクを伴います。
A/Bテストなら、一部のユーザーにだけ新パターンを表示して試せるため、大きなリスクを冒すことなく改善案の効果を検証できます。
もし新パターンの成績が悪くても、影響を最小限に抑えることができます。 - 広告の費用対効果(ROAS)を最大化できる
LPのCVRが向上すれば、同じ広告費でもより多くのコンバージョンを獲得できます。
つまり、広告運用とLP改善を連携させることで、広告の費用対効果(ROAS)を最大化できるのです。
A/Bテストによる地道な改善の積み重ねが、最終的に事業全体の利益向上に繋がります。
【初心者でも安心】LPのA/Bテストを成功に導く8ステップ

A/Bテストの重要性が分かったところで、次はいよいよ実践です。
「何から手をつければいいの?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、心配ありません。
この章では、A/Bテストを成功させるための手順を8つのステップに分けて、初心者にも分かりやすく解説します。
この流れに沿って進めることで、誰でも計画的にテストを実施し、改善サイクル(PDCA)を回せるようになります。
- Step1. 目的とKPIの明確化
- Step2. 現状分析と課題の特定
- Step3. 改善の仮説を立てる
- Step4. テストパターンの作成
- Step5. テストの設計とツールの設定
- Step6. テストの実施
- Step7. 結果の分析と統計的有意性の確認
- Step8. 改善の実施と次のPDCAへ
Step1. 目的とKPIの明確化
まず最初に、今回のA/Bテストで「何を達成したいのか」を具体的に定義します。
ゴールが曖昧なままでは、正しい評価ができません。
目的を明確にし、それを測定するための重要業績評価指標(KPI)を設定しましょう。
| 設定例 | 解説 |
|---|---|
| 悪い例 👎 | LPのCVRを上げる |
| 良い例 👍 | CTAボタンの文言を変更し、ボタンのクリック率を5%向上させる |
このように、具体的で測定可能な目標を立てることが、成功への第一歩です。
Step2. 現状分析と課題の特定(GA4・ヒートマップ活用)
次に、やみくもに改善案を考えるのではなく、データに基づいてLPの現状を分析し、課題を特定します。
この工程を丁寧に行うことで、効果的な仮説立案に繋がります。
主に、以下のツールを活用します。
- Google Analytics 4 (GA4):
ユーザーがどのページで離脱しているか、ページの滞在時間はどれくらいか、コンバージョンに至るまでの経路などを分析できます。
特に離脱率が高いページや、滞在時間が極端に短いページは改善の余地が大きいと考えられます。 - ヒートマップツール:
ユーザーがページのどこをよく見ているか(アテンションヒートマップ)、どこをクリックしているか(クリックヒートマップ)、どこまでスクロールしたか(スクロールヒートマップ)を視覚的に把握できます。
「読まれていると思っていた箇所が読まれていない」「クリックできない画像がクリックされている」といった意外な発見があります。
これらのデータから、「ファーストビューでの離脱が多い」「CTAボタンがクリックされていない」といった具体的な課題を見つけ出します。
Step3. 改善の仮説を立てる
課題が特定できたら、次はその原因を考え、どうすれば改善できるかという「仮説」を立てます。
質の高い仮説を立てることが、A/Bテストの成否を大きく左右します。
仮説は以下のフレームワークで考えると良いでしょう。
「[課題]は、[原因]が理由だと考えられる。そのため、[改善策]を行えば、ユーザーの[心理や行動の変化]が起こり、[KPI]が改善されるはずだ」
仮説の例:
「ファーストビューの直帰率が高い(課題)のは、メインビジュアルの人物写真がターゲット層と合っておらず、自分事として捉えられていない(原因)からだ。そこで、メインビジュアルをターゲット層と同じ年代の人物が笑顔で製品を使っている写真に変更すれば(改善策)、ユーザーが親近感を抱き、続きを読む意欲が湧く(心理や行動の変化)ため、スクロール率が向上し直帰率が低下する(KPI改善)はずだ」
Step4. テストパターンの作成
立てた仮説に基づいて、改善を加えたBパターンを作成します。
現在のLPがAパターン(オリジナル)となります。
ここで非常に重要な原則が「一度に変更する要素(変数)は1つに絞る」ことです。
例えば、キャッチコピーとボタンの色を同時に変更してしまうと、たとえ成果が上がったとしても、どちらの要素が貢献したのかが分からなくなってしまいます。
どの変更が効果的だったのかを正確に知るために、必ず1つの要素ずつテストしましょう。
Step5. テストの設計とツールの設定
テストパターンが準備できたら、A/Bテストツールでテストの設計を行います。
主に以下のような項目を設定します。
- トラフィックの配分: AパターンとBパターンに、それぞれ何%のユーザーを振り分けるか設定します(通常は50%:50%)。
- テスト対象: 全てのユーザーを対象にするのか、新規ユーザーのみ、あるいは特定の広告から流入したユーザーのみなど、対象を絞り込みます。
- コンバージョン目標: 何をもって「成果」とするかを設定します。「サンクスページへの到達」や「特定ボタンのクリック」などが一般的です。
これらの設定を正しく行うことで、信頼性の高いデータを収集できます。
Step6. テストの実施
ツールの設定が完了したら、いよいよテストを開始します。
テスト期間中は、結果が気になっても焦らずに、統計的に意味のあるデータ量(サンプルサイズ)が集まるまで待ちましょう。
一般的に、テスト期間は最低でも1週間、トラフィック量によっては2週間から1ヶ月程度が目安とされています。
また、テスト期間中に特定の広告配信を強化するなど、他の要因が結果に影響を与えないように注意することも重要です。
Step7. 結果の分析と統計的有意性の確認
テスト期間が終了したら、結果を分析します。
ここで注意したいのが、単に「BパターンのCVRがAパターンより高かったからBの勝ち」と安易に判断しないことです。
その差が「偶然」によるものではないことを、統計的に証明する必要があります。
これを「統計的有意性」と呼びます。
専門的に聞こえますが、要は「その結果が、まぐれ当たりではない確率」を確かめる作業です。
一般的に「有意水準5%未満(p値 < 0.05)」、つまり「偶然である可能性が5%未満」であれば、その差には意味があると判断されます。
現在では、無料で使える統計的有意性の計算ツールも多く存在するため、専門家でなくても簡単に確認できます。
| テスト結果 | 判断 | 次のアクション |
|---|---|---|
| Bが勝ち(有意差あり) | 改善成功 | Bパターンを本実装し、次の改善箇所を探す |
| Bが負け(有意差あり) | 改善失敗 | 仮説が間違っていたと判断し、別の仮説で再テスト |
| 差がない(有意差なし) | 引き分け | どちらを採用しても良いが、学びは少ない。テスト期間や変更内容を見直す |
Step8. 改善の実施と次のPDCAへ
テスト結果に基づき、勝利したパターンを本番のLPに実装します。
これで一つの改善サイクルが完了しました。
しかし、LPの改善に終わりはありません。
テスト結果から得られた「ユーザーはこういう表現を好むのか」といった学びを元に、また新たな課題を見つけ、次の仮説を立て、テストを繰り返していきます。
この継続的なPDCAサイクルこそが、LPを最強の営業ツールへと育て上げる鍵となります。
CVR改善に直結!効果が出やすいLPのA/Bテスト箇所と仮説例

「A/Bテストのやり方は分かったけど、具体的にどこから手をつければ効果が出やすいの?」
そう考える方のために、この章では改善インパクトが大きく、CVR向上に繋がりやすいLPのテスト箇所を4つ、優先度の高い順にご紹介します。
具体的な仮説例も挙げていますので、ぜひご自身のLPに当てはめて考えてみてください。
- ① ファーストビュー(キャッチコピー、メインビジュアル)
- ② CTA(ボタンの文言、色、配置)
- ③ フォーム
- ④ コンテンツ・オファー(事例、料金、特典)
① ファーストビュー(キャッチコピー、メインビジュアル)
ファーストビューは、ユーザーがLPにアクセスして最初に目にする領域です。
ここで「自分に関係がありそうだ」と思ってもらえなければ、ユーザーは即座に離脱してしまいます。
まさにLPの顔であり、最も重要なテスト箇所です。
仮説例:
- キャッチコピー: 製品の機能(スペック)を訴求するより、顧客が得られる未来(ベネフィット)を訴求した方が、ターゲットの心に響くのではないか。
- メインビジュアル: 製品写真よりも、製品を使って満足しているユーザーの写真を見せた方が、利用イメージが湧きやすいのではないか。
成功事例:
あるBtoBのSaaS企業では、LPのターゲットを「乗り換え検討ユーザー」に絞り、競合との違いを明確にしたキャッチコピーに変更したところ、広告パフォーマンスが約2倍に向上したという実績があります。
② CTA(ボタンの文言、色、配置)
CTA(Call To Action:行動喚起)は、ユーザーに最終的な行動(購入、問い合わせなど)を促すためのボタンやリンクです。
CVRに直接的な影響を与えるため、非常に重要なテスト箇所です。
テスト要素の例:
- 文言: 「資料請求」→「無料でノウハウ資料をダウンロード」のように、ユーザーにとってのメリットや手軽さを伝える言葉に変える。
- 色: 周囲の色と対照的で目立つ色(補色)を使うとクリックされやすいのではないか。
- マイクロコピー: ボタンの近くに「いつでも解約できます」「1分で入力完了」といった安心感を促す一言を追加する。
成功事例:
ある金融サービスでは、CTAボタンの文言を「口座開設はこちら」から「最短5分で口座開設」に変更したところ、クリック率が大幅に改善し、口座開設数15%増加に繋がりました。
③ フォーム
入力フォームは、コンバージョンにおける最後の関門です。
「入力が面倒だ」と思われた瞬間に、ユーザーは離脱してしまいます。
フォームの入力しやすさを改善するEFO(Entry Form Optimization)は、CVRを底上げする上で非常に効果的です。
| 改善ポイント | 仮説例 |
|---|---|
| 項目数 | 必須項目を最小限に絞れば、ユーザーの入力負担が減り、完了率が上がるのではないか。 |
| ラベルとプレースホルダー | 項目名の隣に入力例(プレースホルダー)を明記すれば、ユーザーが迷わず入力できるのではないか。 |
| エラー表示 | エラー発生時に、どこが・なぜ間違っているのかをリアルタイムで分かりやすく示せば、離脱を防げるのではないか。 |
| ボタンの文言 | 「送信」よりも「入力内容を確認する」のように、次のステップが分かる文言の方が安心感を与えられるのではないか。 |
④ コンテンツ・オファー(事例、料金、特典)
ファーストビューやCTAだけでなく、LPの「中身」であるコンテンツ自体も重要なテスト対象です。
ユーザーの不安を解消し、納得感を高めるための要素をテストします。
テスト要素の例:
- 顧客事例: BtoCなら個人の感想、BtoBなら企業の導入事例を掲載する。また、事例の掲載順序を変えるだけでも反応が変わることがあります。
- 料金プラン: 複数のプランがある場合、最も推奨したいプランを目立たせる、あるいはプランの並び順を変えることで、選択されるプランが変わるかテストします。
- オファー(特典): 「期間限定で初期費用無料」「今なら〇〇プレゼント」といった特典の有無や内容を変更し、緊急性やお得感を演出します。
【失敗しないために】A/Bテスト実施前に知っておくべき7つの注意点

A/Bテストは強力な手法ですが、やり方を間違えると時間と労力が無駄になってしまうこともあります。
ここでは、初心者が陥りがちな失敗を避け、効果的なテストを行うために知っておくべき7つの注意点を解説します。
これらを事前に理解しておくことで、テストの精度を高めることができます。
- 明確な仮説なしにテストを始めない
「なんとなくボタンの色を変えてみよう」といった仮説なきテストは、ただの運試しです。
必ず「現状分析→課題特定→仮説立案」のプロセスを踏み、目的意識を持ってテストに臨みましょう。 - 一度に多くの要素をテストしない
前述の通り、複数の要素を同時に変更すると、どの変更が結果に影響したのか特定できません。
効果検証を正確に行うため、テストする変数は一つに絞るのが鉄則です。 - テスト期間が短すぎる・サンプルサイズが不足している
早く結果を知りたい気持ちは分かりますが、データ量が不十分な段階で結論を出すのは危険です[^4]。
曜日によるアクセスの変動なども考慮し、最低でも1〜2週間はテストを継続し、統計的に信頼できるサンプルサイズを確保しましょう。 - テストツールがページ表示速度に与える影響を考慮する
A/Bテストツールによっては、スクリプトの読み込みが原因でページの表示速度が遅くなることがあります。
表示速度の低下はユーザー体験を損ない、CVRに悪影響を与える可能性があるため、ツールの設定を最適化し、影響を最小限に抑える工夫が必要です。 - テスト結果を無視したり、主観で判断したりしない
「自分はこちらのデザインの方が好きだ」といった個人的な好みや、「この程度の差なら…」という感覚でテスト結果を無視してはいけません。
A/Bテストの最大のメリットは客観性にあります。データが示した結果を真摯に受け止め、次のアクションを決定しましょう。 - 外部要因を考慮に入れる
大型連休、季節的なイベント、テレビCMの放映など、外部要因がテスト結果に影響を与えることがあります[^1]。
テスト期間中に大きな外部要因がなかったかを確認し、結果を解釈する際に考慮に入れましょう。 - モバイルでの見え方も必ず確認する
今やアクセスの大半はスマートフォン経由です。
PCでテストパターンを作成した後、必ずスマートフォンでも表示崩れがないか、操作しにくくないかを確認しましょう。
可能であれば、PCとモバイルで別々にテストを実施するのが理想的です。
【2024年最新】Googleオプティマイズ代替!LP A/Bテストツールおすすめ7選
2023年9月にGoogleオプティマイズがサービスを終了し、多くのWeb担当者が代替ツール探しに迫られました。
幸い、現在では国内外で高機能なA/Bテストツールが多数提供されています。
この章では、主要な代替ツールを7つピックアップし、それぞれの特徴を比較します。
自社の予算や目的に合ったツール選びの参考にしてください。
| ツール名 | 主な特徴 | 価格帯 | こんな企業におすすめ |
|---|---|---|---|
| Optimizely | 高度な多変量テスト、パーソナライズ、サーバーサイドテストなどエンタープライズ向け機能が豊富。 | 高価格帯 | データ分析専門チームがいる大企業、複雑なテスト要件を持つ企業。 |
| VWO | A/Bテストに加えヒートマップやセッション録画など、総合的なコンバージョン改善機能を持つ。 | 中価格帯〜 | A/Bテストだけでなく、ユーザー行動分析も一つのツールで完結させたい企業。 |
| AB Tasty | AIを活用した予測機能や、顧客体験のパーソナライズ機能が充実。 | 中〜高価格帯 | ユーザーセグメントごとのきめ細やかなアプローチでLTVを最大化したい企業。 |
| SiTest | 日本国産ツールで、管理画面やサポートが日本語。ヒートマップやEFO機能も統合されている。 | 無料プランあり | 初めてツールを導入する企業、日本語サポートを重視する中小企業。 |
| DLPO | LP改善に特化したツール。専門家によるテスト設計や運用代行のコンサルティングサービスも提供。 | 要問い合わせ | LPOに特化して成果を出したい企業、社内にテスト運用のリソースがない企業。 |
| Convert Experiences | 豊富な連携機能と柔軟なセグメンテーションが特徴。買い切りプランもあり、コストを抑えやすい。 | 中価格帯 | 様々な外部ツールと連携してデータ活用したい企業、コストパフォーマンスを重視する企業。 |
| ABlytics | AIがテストパターンを自動で最適化してくれるなど、AIによる効率化を前面に打ち出している。 | 要問い合わせ | 最新のAI技術を活用して、テスト運用工数を削減しつつ成果を出したい企業。 |
ツール選定の際は、無料トライアルなどを活用して、実際の管理画面の使いやすさや、自社のLPとの相性を確認することをおすすめします。
まとめ:データに基づいたLP改善で、着実に成果を上げよう
この記事では、LPのA/Bテストの基本から具体的な実践方法、ツールの選び方までを解説しました。
- A/Bテストは、データに基づきLPを客観的に改善する強力な手法である。
- 成功の鍵は「目的設定→分析→仮説→検証」という正しいステップを踏むこと。
- ファーストビューやCTAなど、インパクトの大きい箇所からテストするのが効果的。
- 失敗を避けるには、統計的有意性の確認やテスト期間の確保などの注意点を守ることが重要。
- Googleオプティマイズ終了後も、自社に合った代替ツールは多数存在する。
LPの改善は、一度行えば終わりというものではありません。
A/Bテストを通じてユーザーへの理解を深め、継続的に改善のサイクルを回し続けることで、LPはより強力な成果を生み出す資産へと成長していきます。
まずはこの記事を参考に、自社LPの現状分析から始めてみませんか。
データという羅針盤を手に、着実な成果向上を目指しましょう。